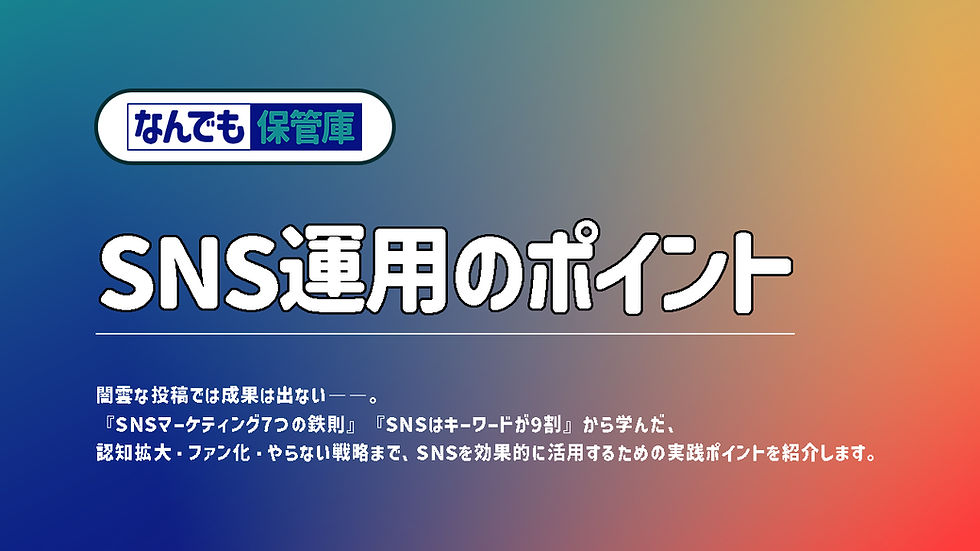「こども家庭庁」とは何か?日本のこどもが直面している現状
- のろ

- 2025年2月17日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年5月15日
はじめに
ニュース記事を読んでいると、「こども家庭庁」という言葉が目に留まりました。ふと考えてみると、名前は知っているものの、具体的にどのような活動をしているのかよくわからない…。そこで今回は、「こども家庭庁」について調べてみることにしました。
さまざまな活動を行っているようですが、それ以上にこの組織が発足した背景が興味深いと感じたため、背景となる日本のこどもに関する課題についてまとめました。
こども家庭庁について
今の社会では、少子化・虐待・不登校・いじめなど、こどもを取り巻く状況が非常に深刻化しています。一人ひとりのこどもが幸せに暮らせるよう、こどもを中心とした取り組みや政策を推進する「こどもまんなか社会」の実現を目指し、2023年4月に「こども家庭庁」が設置されました。
公式サイトの政策分野を見てみると、「こども・子育て支援」「少子化対策」「児童虐待防止対策」などが挙げられています。簡単に言えば、こども家庭庁はこどもに関する幅広い課題に取り組む行政機関といえるでしょう。
次元の異なる少子化
厚生労働省の人口動態統計によると、日本の出生数は以下のように推移しています。

日本の出生数は戦後から減少の一途をたどっていますが、近年はその減少スピードが加速しており、従来の政策では歯止めがかかっていないことが明らかです。
2030年代には若年人口の急減が予測され、少子化を食い止めることはさらに難しくなると考えられています。そのため、2030年代に入るまでの数年間が、少子化対策の「最後のチャンス」と位置付けられています。
本白書には、「少子化が進むと、国の人口が減少し、現在の社会のしくみを維持することが難しくなる」と記載されています。出生数の推移を見ても、今の制度を維持することは現実的に困難でしょう。むしろ、新しい社会のしくみを模索し、構築していく方が、より有意義であるように思われます。
日本の若者の価値観
こども家庭庁が実施した「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」によると、日本の若者は「私は、自分自身に満足している」と思う割合が、他国と比べて顕著に低いことが明らかになりました。

この結果から、日本の若年層は全体的に自己肯定感が低く、ネガティブな傾向が強いと推察されます。謙虚さや努力を重視する日本文化に加え、SNSの普及による周囲との比較意識の助長、少子化や経済停滞による将来への不安など、さまざまな要因が複合的に影響していると考えられます。
こうした問題は行政の対応が求められる領域とも重なっており、こども家庭庁の役割や取り組みに対する期待も大きいと言えるでしょう。
日本の親子関係はどうか
全国の児童相談所における虐待相談対応件数は、以下のように年々増加しています。

出生数が減少しているにもかかわらず、虐待相談対応件数が増加していることに違和感を覚えます。これは、児童虐待防止法の改正により、「しつけ目的の体罰の禁止」や「面前DVの虐待認定」など、以前よりも広範囲の行為が虐待と認識されるようになったことが影響していると考えられます。要するに、虐待そのものが増加しているというよりも、社会の変化によって「発覚しやすくなった」と解釈するのが適切かもしれません。
いじめや不登校の件数
文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を見ると、いじめの認知件数は以下のように推移しています。

また、不登校児童生徒数は以下のように推移しています。

いじめ防止対策推進法の改正や、不登校に対する認識の変化により、以前よりも広範囲のケースがいじめや不登校として認識されるようになったことが影響しています。また、学校のいじめ報告義務の強化や、フリースクールなどの普及によるデータの精度向上も関係していると考えられます。これらも虐待と同様に、社会の変化によって「見えやすくなった」と解釈できます。
自ら命を絶つこども
自殺の統計を見てみると、こども(小学生〜高校生)の自殺者数も増加していることが分かります。

「いじめ」「不登校」「虐待」は、法改正や社会の認識の変化によって統計上の件数が増えて見えることがあります。しかし、自殺の件数は警察庁の統計に基づいており、こうした影響をほぼ受けないため、実際に増加している可能性が非常に高いと考えられます。この傾向は、日本の若者に特有の「自己肯定感の低さ」と深く関係しているように感じます。
さいごに
まず大前提として、日本の若者に対する「自己肯定感を高める教育」は不可欠だといえます。こども家庭庁には、この領域に重点的に取り組んでほしいと感じます。
「いじめ」「不登校」「虐待」などの問題はすべて増加傾向にあり、日本の未来に希望を持てないこどもが増えているのも無理はありません。しかし、過度に悲観的になるのは賢明ではないでしょう。従来の統計の精度が低かった可能性もあり、単に以前よりも実態が可視化されただけかもしれません。また、定義の拡大によって統計に含まれるそもそもの母数が増えています。
一方で、少子化に歯止めがかかっていないこと、日本の若者が他国と比べてネガティブであること、自殺を選ぶ若者が増えていることは、社会の認識や統計の取り方に左右されにくい確実な課題です。これらに対する具体的な対策を早急に進めてほしいと思います。