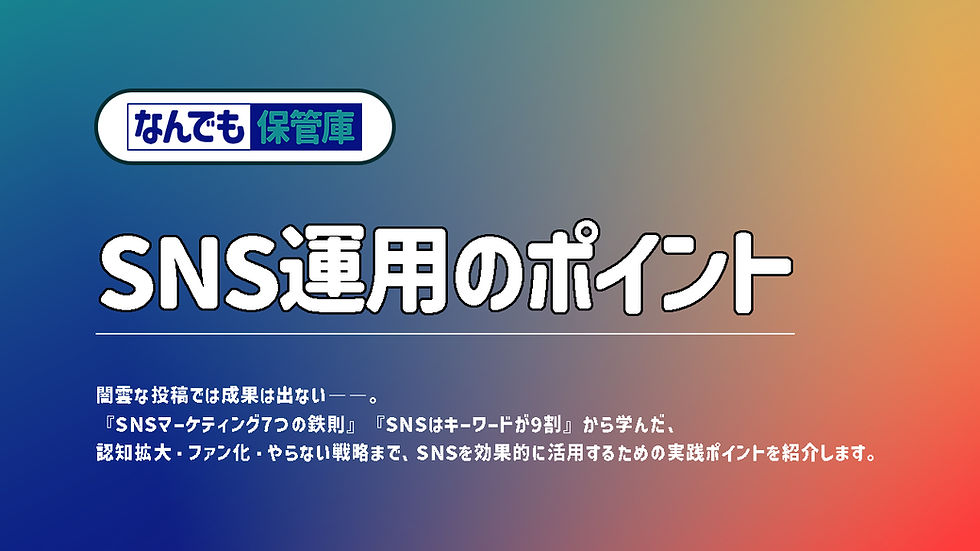子どもが親しみやすいICT教材とは?マルチデバイス教育の視点
- のろ

- 2024年11月24日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月7日
はじめに
今回は教育ICTを通じて「新しい学び」を提案する教育者チームであるiTeachers(アイ・ティーチャーズ)が配信している動画の中から、面白そうなものを見つけたので視聴してみました。
コロナ禍を経て、従来は対面のみだった教育の場に、オンラインという新たな選択肢が加わりました。一方で、フルリモートを採用していた民間企業が、元の出社体制へ戻るケースも見られるようになり、ITの進化と社会情勢の変化が交錯する今、教育とデジタルの関わり方はさらに注目を集めています。
そのような社会の中で、PCなどの電子機器を活用する情報教育は、どのように進化を遂げているのでしょうか。その実態について語った東京都市大学付属小学校の清水哲治先生によるプレゼン「子どもたちの好き嫌いを無くすために!」をまとめてみました。
情報の授業とは
学習指導要領において、「情報活用能力」は学習の基盤となる資質・能力と位置付けられています。近年、その重要性はますます高まりつつあり、情報教育の充実や教科指導におけるICTの活用、教育の情報化が積極的に進められています。
この学習指導要領の下で、文科省では「教育の情報化に関する手引」を作成しています。本手引の中心的なテーマの一つが「子どもたちの情報活用能力の育成(情報教育)」です。具体的な内容を見ると「コンピュータの基本操作の習得」「情報モラルの理解」「プログラミング的思考の育成」等があり、これらの内容を学ぶ場として、情報の授業が設けられています。
子どもが親しみやすい教材
同校で毎月1回行われる小学校1~3年生の情報メディアの授業では、子どもたちが楽しくコンピュータの基本操作を身につけられる教材が使われています。例えば、マウス操作に慣れるためのマウスポインターを利用するゲームやお絵かき、キーボード入力に慣れるためのタイピングゲーム。これらの教材は、遊び感覚で取り組めるため、子どもたちが積極的に学びやすい工夫がされています。

マルチデバイスへのこだわり
プレゼンの中で「1人1台のiPad配備」「メディア教室に共有PCを40台完備」と述べられており、十分なICT環境が整備されていることがわかります。
タブレットとPCの両方に触れることで、子どもたちはタッチ操作やマウス操作といった多様な体験ができます。特にお絵かきでは、図形を活用するベクター形式はマウス操作、フリーハンドで描くラスター形式はタッチ操作が適しているなど、操作方法やデバイスごとの適正を実感する良い機会となっています。

これらの取り組みは、子どもたちが将来、学びの目的に応じて最適なツールを選択できる力を育むことを目指しています。単なるデバイス操作の習得に留まらず、ICTを効果的に活用する基盤を築く重要なステップとなっています。
さいごに
私が小学生の頃は、パソコン室には1クラス分のPCがありましたが、1人1台のデバイスが支給される環境はありませんでした。現在は、デバイスに触れるといった行為が、子どもたちにとってより身近なものに変わってきているのでしょう。
一方で授業の内容を見てみると、私たちの時代とあまり変わっていない印象でした。これは教え手である先生のリテラシーや意識が、あまり変化していないためだと思います。
時代の経過とともに、デジタルコンテンツの充実度も増しています。これらを活用し、子どもたちが未来に向けた力を身につけられるような、時代に即した意味のある教育へと進化してほしいです。