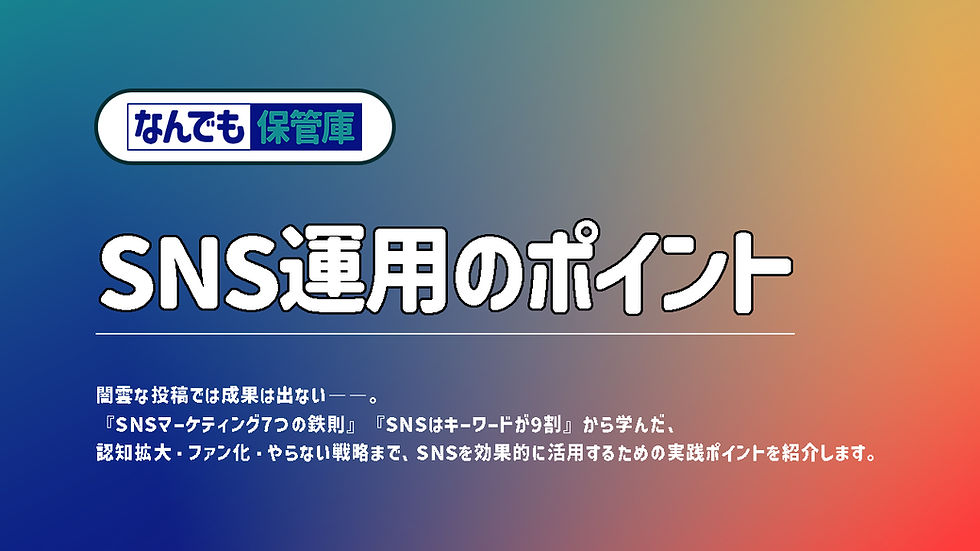教育現場での1人1台端末のリアルとは?市川工業高校の取り組み
- のろ

- 2025年1月7日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年5月15日
はじめに
今回も教育ICTを通じて「新しい学び」を提案する教育者チームであるiTeachers(アイ・ティーチャーズ)が配信している動画の中から、面白そうなものを見つけたので視聴してみました。
GIGAスクール構想は、文部科学省が2019年(令和元年)に発表した教育のICT化を目的とした取り組みです。この構想では、児童生徒一人ひとりに学習用端末を配備し、高速ネットワーク環境を整備するなど、充実したICT環境の構築を目指しています。また、教員や児童生徒のITスキル向上や情報モラル教育を推進し、未来社会で必要とされる能力の育成に取り組んでいます。
全国の学校でさまざまな取り組みが進む中、MDMを活用した管理体制を確立している事例もあります。今回は、1人1台端末の導入から管理システムの運用までを語った、千葉県立市川工業高等学校の片岡伸一氏によるプレゼン「よく見ろ。これが市川工業高校だ 〜REBEL工業高校〜」をまとめました。
1人1台端末の導入実態
全国の小中学校では、児童生徒1人1台の端末整備が進められ、令和4年度末時点で整備が完了しています。高等学校においても、整備が推進されており、令和6年度時点で高い整備率を達成しています。

生徒端末の支給形式には、公費による配備のほか、BYAD(学校指定の端末を購入)やBYOD(個人所有の端末を持ち込む)といった保護者負担の形態があります。全国の都道府県によって支給形式は異なりますが、千葉県では保護者負担での支給が採用されており、市川工業高校ではBYOD形式でiPadを保護者に用意してもらっています。
1人1台端末の導入にあたっては、入学者やその保護者への案内が不可欠です。さらに、導入要件の検討と並行して、中学校への周知活動も求められます。
システムを駆使した管理体制
同校では、MDM(Mobile Device Management)とASM(Apple School Manager)を活用して、生徒端末を一元管理しています。
MDMは、スマートフォンやタブレットなどの端末を集中管理するためのシステムです。一方、ASMはAppleが提供する教育機関向けの管理ツールで、特にApple製デバイスの管理に特化しています。この2つを連携させることで、効率的な管理が可能になります。

プレゼン内で具体的な管理方法については語られませんが、「Jamf Pro」という言葉が出てきたことから、同校では「Jamf Pro × Apple School Manager」の体制で運用していると考えられます。
全校で一体となり実現したiPad導入
導入日は1年生の授業を1日休止し、「iPadの日」と題した特別時間割を設けて端末導入を行いました。この日には、アプリやネットワークの初期設定、基本操作の練習が行われ、生徒がスムーズに端末を活用できるようサポートしました。
初年度は教職員がこれらの説明を担当しましたが、次年度からは上級生が下級生に説明する形式へと変更し、生徒間の協力や自主性を育む仕組みが導入されました。
日常の中で取り入れているデジタル活用
簡単な連絡にはチャットツールを活用するなど、連絡手段のデジタル化が進んでいます。また、資料作成での画像生成や卒業研究におけるコーディング作業などにAI技術を積極的に取り入れ、効率向上と高度なスキルの習得を目指しています。
さらに、各種サービスの利用に際しては、使用ルールを策定し、それに基づいた運用を徹底することで、適切かつ安全な活用を実現しています。
ICTを活用する際に重要なこと
ICTを教育現場で活用するには、学校が自分事として捉え、自校の教育理念に基づいて積極的に取り組むことが重要です。市川工業高校では、入学前説明会において協力業者に頼らず、職員が直接説明責任を果たす姿勢を示しています。
また、小さなきっかけを大切にし、教職員や生徒全員を巻き込みながら輪を広げていくことで、学校全体でのICT活用を円滑に進めることができます。

さいごに
義務教育段階だけでなく、高等学校でも1人1台端末の整備がかなり進んでいる現状には驚きを感じました。教育現場でのICT活用においては、「自分事として捉える」「輪を広げていく」といった考え方が非常に重要です。これらの考え方は企業のDXとも通じるものがあり、民間企業と公共教育機関がより深く連携することで、教育現場でのICT活用が新たな可能性を広げていくような気がしています。
一方で、デジタル化を支える体制には依然として課題が多いのも事実です。特に、デジタル技術に馴染みが薄い世代が権限を持つ現状では、教育分野でのデジタル化推進は難航するかもしれません。しかし、デジタルコンテンツが充実している現代において、時代に即した意味のある教育へと進化していくことを期待しています。