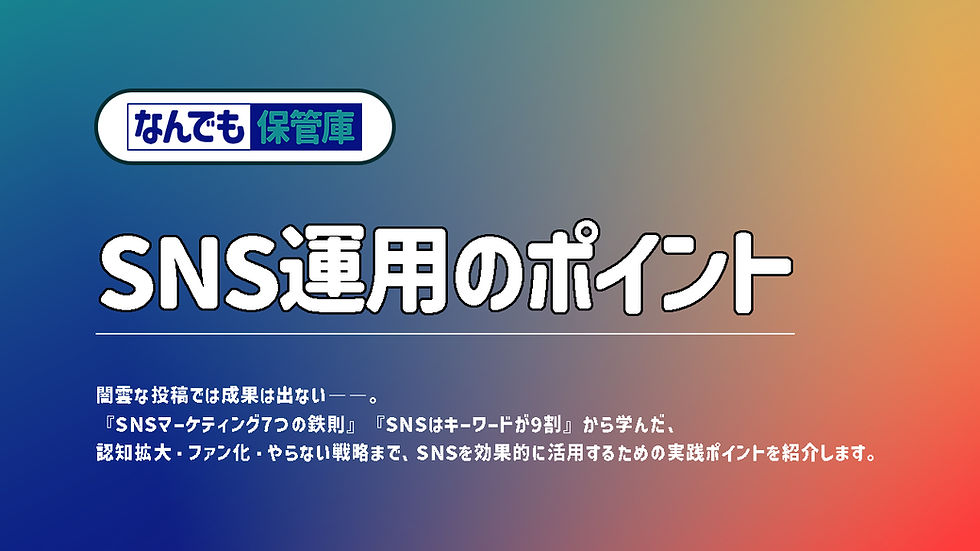ポッドキャストは教育現場で活用できるか?学びの可能性を探る
- のろ

- 2024年11月14日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年5月15日
はじめに
教育関係の得意先が多い職業柄、教育系の情報収集は定期的に行っています。
今回は教育ICTを通じて「新しい学び」を提案する教育者チームであるiTeachers(アイ・ティーチャーズ)が配信している動画の中から、面白そうなものを見つけたので視聴してみました。
近年、耳にすることも多くなってきた「ポッドキャスト」という言葉。音声メディアであるこのコンテンツは、ラジオと同様に「ながら」でも視聴できるため、忙しい生活の中にも取り入れやすいメリットがあります。そんなポッドキャストは、果たして教育の現場で活躍できるのか。注目されるこのコンテンツについて掘り下げた、西武学園文理高等学校の国語科教員笠原氏によるプレゼン「学びの可能性を広げるポッドキャスト」をまとめてみました。
ポッドキャストとは
ポッドキャストとは、インターネットを通じて音声コンテンツを配信するサービスです。ユーザーは好きなときにコンテンツを再生でき、番組のテーマやジャンルも多岐にわたります。要は、YouTubeやNetflixなどの動画配信プラットフォームの音声バージョンというイメージです。

ポッドキャストと似た概念に、ラジオがあります。ラジオとの違いとしては、以下のような点が挙げられます。
①リアルタイム放送:ラジオはリアルタイムで配信されるが、ポッドキャストは見たい時に再生できる
②配信の自由度:放送枠に制限がないので、誰もが好きなコンテンツを容易に配信できる
③広告の形式。ラジオは放送局からの広告が主だが、ポッドキャストはスポンサー広告がメイン
ラジオとポッドキャストの関係性は、テレビと動画配信プラットフォーム(YouTubeやNetflix等)の関係性に非常によく似ています。
教育とポッドキャストの関係
プレゼンの中で「本校は一人に一台ずつChromebookが支給されている」とありました。同校の公式サイトを見てみても、ポッドキャスト/動画/開発/デザインなど様々なプロジェクトの取り組みがあり、教育ICTに関して前向きな姿勢の組織であることが伺えます。このしっかりしたICTへの意識と、潤沢な投資が形成する安定した土台は、私立ならではなのかなと思います。
笠原氏は教育におけるポッドキャストの役割として、以下の2点を挙げています。
①授業が抽象的で理解しづらい際の補助教材としての役割
②授業が将来何の役に立つかイメージできない際の一つの回答としての役割
特に②は、授業と社会を具体的に繋げる手段として、より一層の活躍が期待できます。
ポッドキャストの具体的な活用方法
インプットの例では、先にも述べましたが参考資料や探究資料等、補助教材としてポッドキャストを利用する方法が薦められています。動画学習が普及した近年では、非常にイメージしやすい利用方法と言えます。
アウトプットの例では、生徒自らポッドキャストを作成する創作活動が挙げられています。企画→調査(ファクトチェック)→台本作成→録音→編集といった一通りの制作工程が経験できる点。情報発信することで伴う責任を身をもって認識できる点。ものづくりの面白さを味わえる点が魅力です。

さいごに
私は高校時代、片道1時間かけて自転車で通学していました。通学中はよくラジオを聴いていましたが、この時間をポッドキャストで学習にあてていれば、今より少しは賢くなったような気もします。
また、同校の取り組みでは、生徒たちが作ったポッドキャストを聴き合うこともしているようで、交換ノートの現代版みたいで面白いそうだなと感じました。
先生や生徒のITリテラシーや、その学校のICTへの意識に依存するため、ポッドキャストを教育に取り入れる難易度はまだまだ高いように感じます。いつか教材選びの当たり前の選択肢として、より個別具体的な教育支援の解決策として、ポッドキャストという道が開けていくと良いと思います。