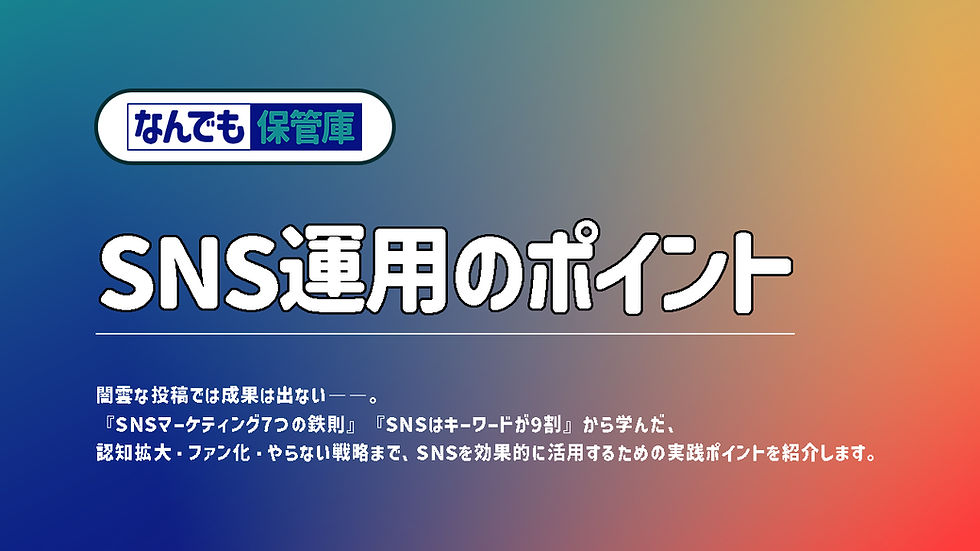不登校問題に迫る|フリースクールとペダゴーが切り拓く新たな教育
- のろ

- 2024年11月5日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年8月7日
はじめに
実家に帰ったら母が「不登校」がテーマの講演会に参加するらしく、面白そうだったのでついて行ってみました。主催は”とちぎと周辺地域のあらゆる職種、普通の人による、医療・介護を通じて地域での暮らしを支えるための勉強会・交流会”を実施している団体である「在宅緩和ケアとちぎ」。第12回夏季講演会(夏合宿)のプログラムの一部を、一般公開しているようでした。
県内の医療・教育関係者が多い印象で、少々内輪のノリも感じる進行でしたが、当日での急遽参加にも関わらず温かく迎え入れてくれました。2つの講義を拝聴し、参加費も500円と非常に満足感がありました。
「フリースクール」という新しい学校の形
1つ目の講義は、NPO法人キーデザイン代表理事の土橋優平氏による「不登校が増える今、私たち大人が子どもにできること」でした。様々な社会貢献をしている同法人の理事である土橋氏が、1993年生まれというのだから驚きです。
本講義は「現在は子どもの5人に1人は不登校」という言葉から始まりました。学校という環境に馴染めず、助けを求めることもできず、社会からぞんざいに扱われてしまう親子は稀な存在ではありません。同法人はこの問題に直面している親子を救うべく、新しい学校の形であるフリースクールを立ち上げました。フリースクールとは、行政が認めた教育機関ではなく民間が運営する教育施設を指します。要するに、小中学校などの義務教育の仕組みに乗れない子どもと親の受け皿になっている場所です。最近では、フリースクールを卒業することで、教育機関を卒業したとみなす事例もあるそうです。

土橋氏は「課題解決は安心の土台が前提」と述べています。確かに小中学校などの教育機関では、先生と生徒の関係構築ができていない状況で、問題解決に向けたアクションをしてしまうことが多いように思います。信頼できない相手に本音を話すことはありませんので、当たり前ですがこれは悪手というわけです。
また、講義の中で「生まれたからには幸せになるべきだ」という言葉があり、この純粋でシンプルな理念に心打たれました。
「ペダゴー」という新たな教育者の形
2つ目の講義は、一般社団法人ペダゴージャパン代表理事の工藤敬子氏による「ペダゴーを通じて子どもたちとともにつくる幸せな学びの場」でした。工藤氏は以前に栃木県教育委員会に在籍していたこともあり、欧州視察の話も含め、講義内容に一定の説得力はあったように思います。
工藤氏は、子どもが不登校になるのは、教育現場に潤いがなく病んでいるからだと述べています。仕組みそのものを変えなければ、この状況は打破できないのではないかと懸念しており、その糸口が「ペダゴー」であるとしています。ペダゴーとは、社会福祉士と保育士の要素を併せ持つ専門家。教育現場における役割分担では、「知性を豊かにする」のが教師で、「感受性を豊かにする」のがペダゴーという位置づけです。確かに、教員採用試験でも知性が重視されるわけで、道徳的な感性の教育には向かない人も教師の中には多いでしょう。そんな中で両方を教師に押し付けるというのは、あまりに酷です。二刀流が成立するのは、宮本武蔵か大谷翔平くらいなものです。
また、幼児教育から義務教育の大きな段差をどう埋めるか。この課題についても、1年生の準備期間としてペダゴーが担任となる「0年生」というような仕組みで解消できないかと述べていました。特に小学校に入ってすぐは、勉強という行為に慣れていくより、社会という息苦しい場所に馴染むことが何より重要です。その手助けをする存在は現状いませんので、ここを埋めてくれる存在には需要があるように思います。
さいごに
義務教育に馴染めなかった親子を支援する対処療法的なフリースクールと、潤いがない教育現場を抜本的に変えようとする原因療法的なペダゴーという対照的な2つのアプローチを聞いて、「不登校」という課題に対する捉え方が広がったように感じます。
この2つの講義を聞いて、不登校の原因は子どもにはないという確信を得ました。一番の問題は、その親にあるように感じました。

「何で学校に行った方が良いのか、行って欲しいのか」を言葉で伝えられない親は多いはずです。今の社会情勢において、自分の子どもが不登校になる可能性は否定できません。子どもを導いてあげられる存在として、最低限自分の考えを持ち、しっかり言葉にできるように準備しておくことは、親としての責任だと思います。