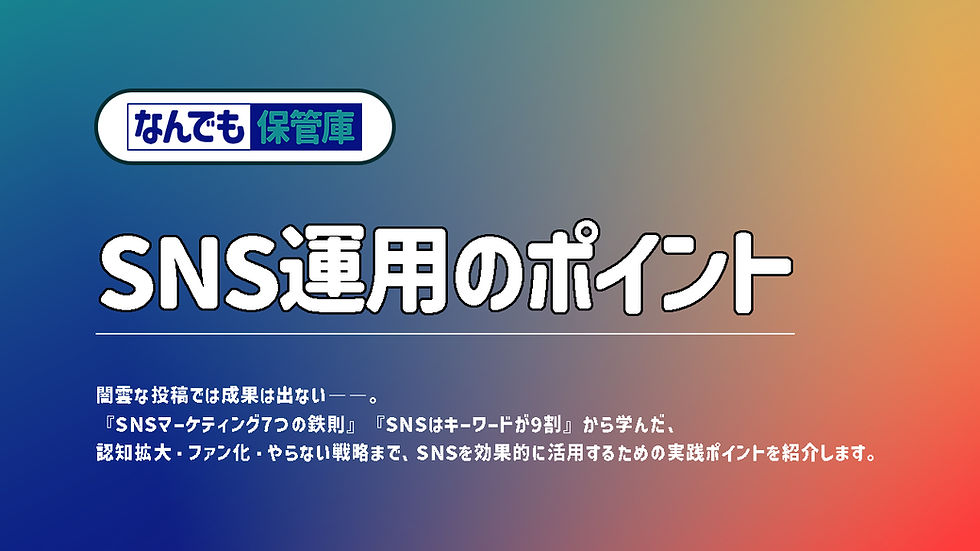働く喜びとは何か?リクルート調査『日本の“働く”の現在地』まとめ
- のろ

- 2024年10月31日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年5月15日
はじめに
私の個人的な働く理由は「生きていくために必要な資金調達」なので、仕事に多くを求めたり、成長して成功したいというような強い欲求はありません。この考え方を特に少数派と思ったことはないですが、ふと実際に社会に出て働いている人は、どんなことを想いながら毎日を過ごしているのか気になりました。
株式会社リクルートでは、2013年より毎年、全国の15歳~64歳の就業者約5,000人~12,000人を対象に仕事に関するアンケート調査を行っています。その11年分の調査結果を基に、2024/4/23に同社から、働く人の喜び実感の状況やその影響要因の変化についてのレポート「日本の“働く”の現在地」が発表されました。今回はこちらのレポートについてまとめてみました。
「働く喜び」を感じている人の推移
「働く喜び」を感じている人の割合は2017年を境に変化を見せています。2013年以降、5年間にわたり減少傾向にあったものの、2018年に増加に転じ、その後42~44%の間で推移。11年間の調査結果を見ると、少なくとも「働く喜び」を実感している人が減っているわけではないということが分かります。

レポートでも触れていますが、この11年間で法律やガイドラインが変更され、社会の在り方が大きく変わっています。特に働き方改革関連法が2018年に成立したことが、ワークライフバランスにプラスな影響を与えているでしょう。
果たして「働く喜び」は必要か?
毎年約80%の人が働く上で「働く喜び」が必要だと回答しています。
「働くと聞いて思い浮かぶ言葉」という問いでは、毎年上位に「報酬」「生活」「お金を稼ぐための手段」があがります。理想を言うのであれば、働きながらにして喜びを感じたいが、実際のところ現実はそう甘くないので割り切っている人がほとんどといったところでしょう。一方で先の質問に対して、「生きがい」や「やりがい」といった回答も多く見受けられます。仕事とプライベートの境界線が曖昧で、自己実現や自己肯定感を高めるための源泉としている人も多いことが分かります。
「働く喜び」を感じるために必要な不安
「キャリアの不安」には、取り除くべき不安と、健全な不安が存在します。「不安を非常に感じる」「不安を全く感じない」のような極端な状態では、働く喜びを感じにくい傾向にあります。そのため、従業員が自らのポテンシャルを最大限に発揮し、充実感を得るためには、適切な挑戦と成長の機会、つまり適度な不安を提供することが重要です。

私の好きなアニメ「PSYCHO-PASS」の第1シーズンでも、槙島聖護がユーストレス欠乏性脳梗塞の件で「適度のストレスは好ましい効果もあるとされてきた。いわゆる人生の張り合い。生きがいと言い直しても良い」と述べています。
組織として取り組むべきこと
従業員が能力を最大限に発揮し、仕事へ積極的に取り組んでおり、周囲とのコミュニケーションが良好であるウェルビーイングが高いと組織は、成果も高いという明確な傾向が見られます。所属している人材がよく成長している組織は、成果やパフォーマンスも良い結果に繋がりやすいといった関係性も示唆されます。組織戦略として「組織開発」や「人材育成」に取り組むことは、組織全体のパフォーマンス向上を実現するために非常に重要です。
「働く喜び」を構成する要素
「働く喜び」を構成する7つの要素は、「信頼関係」「学び・成長」「役割・居場所」「快適な環境」「顧客の期待・感謝」「必要な収入」「社会的影響」となります。
起点は「信頼関係」になります。信頼関係の土台なくして、働く喜びを得ることはできないということです。さらに「快適な環境」は、「社会的影響」「学び・成長」と高い関係性があります。快適な環境下では、意義や学びによる成長を望むようになり、結果的に顧客や組織への貢献実感が生まれます。

また、「働く喜びを感じている人」と「働く喜びを感じていない人」で最も大きな差異を示したのは、「好きなことに関われている」「落ち着いて今の仕事を続けられる」「希望する場所で働けている」「人間的に成長しているという実感がある」「職場に自分の居場所がある」の問いでした。職場が心地良い場所であるか、仕事を前向きに捉えているかが重要で軸であることが分かります。
さいごに
暗い気持ちになるかもと思いながら読み始めましたが、全体を通して前向きになれる明るい印象でした。新鮮さがある情報があったわけではなく、何となくそうだろうなと思っていたことが、実際の調査結果から数字という根拠を持って伝わってきました。
OWNDAYSの田中修治氏も「知っている。できる。やっているは全くの別物」といった言葉を残していますが、理解したうえで継続した実行を維持することで、状況は好転していくのではないかと思います。